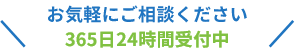減価償却の仕組みと計算方法【中小企業・個人事業主向け】

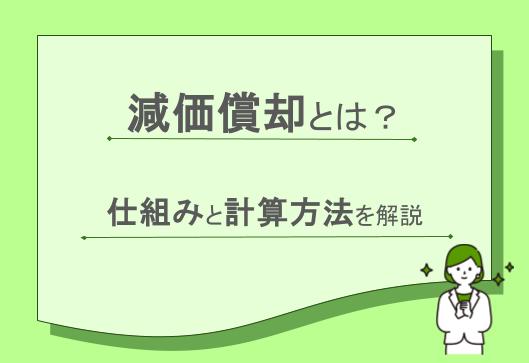
みなさんこんにちは!税理士法人ウィズです!
今回は、中小企業の経営者や個人事業主の皆さまにとって身近でありながら、実務上の処理で悩まれることも多い「減価償却」について、基本的な考え方から実務での対応までわかりやすく解説いたします。
減価償却とは?
事業において建物や車両・機械・パソコンなど、10万円を超える資産を購入する際、それらは時間の経過や使用によって徐々に価値が減少していくと考えられます。
こうした資産を「減価償却資産」といい、その価値の減少分を一定の期間にわたって経費計上する手続きが「減価償却」です。
たとえば、1,000万円の機械を購入した場合、その年に全額を経費にできるわけではありません。使用できる年数に応じて、分割で経費にする必要があります。
減価償却の方法と耐用年数
減価償却には主に以下の2つの方法があります。
・定額法
資産の価値を耐用年数で等分し、毎年同額の減価償却費を計上します。
主に建物・附属設備・構築物や、個人事業主の減価償却で使用されます。
償却額の見通しが立てやすい、シンプルな償却方法です。
・定率法
帳簿価額に一定の率をかけ、減価償却費を計上します、
主に法人が取得した機械装置・車両・器具備品等の減価償却で使用されます。
購入して初めての年は減価償却費が大きく、年数の経過に伴い減少していく方法です。
初年度に経費を大きく計上できるため、設備投資を行った直後に法人税を抑えることが可能です。
また対象の資産を使用できる期間として、国税庁が「法定耐用年数」を定めています。
購入した資産を何年かけて経費にするかは、この法定耐用年数をもとに算出することとなります。
少額の資産の償却方法
前項では通常の減価償却方法をご紹介しましたが、少額の資産は特別な償却方法を適用できる場合があります。
・一括償却資産
10万円以上20万円未満の資産に適用することができます。
本来の耐用年数に関係なく、3年間で均等に経費計上することができます。
※青色・白色申告者共通
・少額減価償却資産
10万円以上30万円未満の資産に適用することが出来ます。
本来の耐用年数に関係なく、全額を経費計上することができます。
※青色申告を行っている中小企業者限定 上限は年間合計300万円まで、令和8年3月31日まで延長中
その他、取得価額が10万円未満、または耐用年数が1年未満の資産は、購入した年度に全額を経費として計上可能です。
金額ごとの具体例
・税込95,000円のノートPCを購入した場合
①消耗品費等にて、全額を経費計上
・税込195,000円のノートPCを購入した場合
以下から選択
①通常の減価償却(法定耐用年数4年)にて経費計上
②一括償却資産として、3年で均等に経費計上
③少額減価償却資産として、全額を経費計上
・税込280,000円のノートPCを購入した場合
以下から選択
①通常の減価償却(法定耐用年数4年)にて経費計上
②少額減価償却資産として、全額を経費計上
実務上の注意点
➀取得価額の判定
資産の取得価額の判定は、自社の経理方式により異なります。
税抜経理の場合は税抜金額、税込経理の場合は税込金額で判定する必要があります。
税込経理を採用し税込価格が10万円を超える場合、減価償却資産の対象となるため注意が必要です。
②通常1単位として取引される単位
個々の金額が10万円未満でも、1単位として取引されるものは合計額で判定することとなります。
応接セット(テーブルと椅子)や、エアコン(本体と室外機)等が該当します。
③付随費用
設置費・配送費等の付随費用が発生した場合、取得価格に含める必要があります。
資産単体では10万円を超えない場合でも、合計で10万円を超える場合は処理区分が変わることがあります。
④事業年度が1年に満たない場合
設立1期目や決算期変更等を行った場合は、事業年度が1年に満たない場合があります。
その場合の少額減価償却資産の上限額は、300万円×事業年度の月数/12が限度となります。
減価償却と償却資産税の関係
減価償却資産は、「償却資産税」という地方税の申告対象になる場合があります。
少額減価償却資産(10〜30万円未満)はその期に全額を経費計上することが可能な一方、償却資産税の対象として申告が必要です。
対して一括償却資産(10〜20万円未満)は、償却資産税の対象外となります。
少額減価償却資産にて全額を即経費計上することは、必ずしも節税に繋がらないと言えます。
まとめ
減価償却は割と聞きなじみのある単語かもしれませんが、実務となると様々な種類があり、それぞれの特徴を知らないと損を被ってしまう可能性もあります。
10万円以上の備品等を購入するする際は上記図表を参考にしつつ、会社運営・資金繰りに役立てていきましょう。
最後までご覧いただきありがとうございました!
税理士法人ウィズでは、顧問契約が無い場合でも税務についてご相談いただける、スポット顧問サービスも展開しております!下記ページよりお気軽にお問い合わせください!
・スポット顧問サービス
https://www.z-with.or.jp/spot-advisory/
過去の減価償却に関するブログはコチラ!