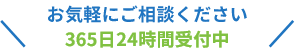ふるさと納税の仕組みと注意点

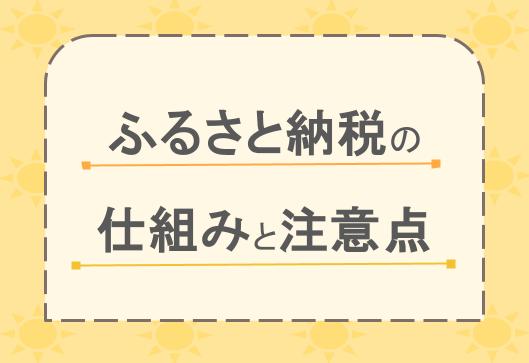
今回は多くのお客様からご相談いただく、「ふるさと納税」について解説いたします。
6月は住民税の改定時期なので今年の確定申告や年末調整に備えて一緒に準備をしていきましょう。
ふるさと納税とは? ─ 制度の概要
ふるさと納税とは、個人が任意の自治体に寄付を行い、その金額のうち一定額について所得税および住民税の控除が受けられる制度です。
2025年(令和7年)中に行った寄付は、2026年(令和8年)6月以降の住民税へ反映されることとなり、税金の前払いのような仕組みになっています。
自己負担額として2,000円が発生してしまいますが、各自治体からさまざまな返礼品を受け取ることができるため、人気を集めている制度です。
控除額の上限に注意
一般的には、寄付額から自己負担額2,000円を除いた全額が控除対象になります。
ただし、控除限度額内であることが前提です。
控除限度額は、以下の要因によって決まります。
・総所得金額等
・家族構成(配偶者や扶養の有無)
・他の所得控除(医療費控除・社会保険料控除等)
また各種ポータルサイトでは、目安となるシミュレーション機能が用意されています。概算で控除限度額を算出できますので、ご活用ください。
ただし、給与収入以外の所得(不動産所得・事業所得等)がある方はそちらも考慮しなければならないため、注意が必要です。
総務省のHPには詳しい計算方法や、年収別の控除限度額の目安も記載されていますので、是非ご活用ください。
総務省 ふるさと納税ホポータルサイト:税金の控除について
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html
ワンストップ特例制度
ふるさと納税という制度は知っているけど、確定申告が面倒…という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
勤め先で年末調整を行っている場合、
確定申告を行う必要がない給与所得者は、年間で自治体の数が5団体以内の寄付であれば、ワンストップ特例の申請により確定申告なしで控除が受けられます。
ただし、下記の点にご注意ください。
・寄付のたびに申請書を自治体へ送付が必要
・6団体以上に寄付した場合は確定申告が必要
・転居や氏名変更がある場合、再申請が必要になることがある
注意点
・控除額を超えて寄付すると「損」をすることも
寄付額が控除上限を超えてしまうと、その分は純粋な「寄付」として扱われます。返礼品は受け取れますが、税金の還付・控除対象にはなりません。
控除の対象になるのはあくまで、「寄附を行った年の所得」です。収入状況に変化がある場合は控除限度額も変動します。
・書類不備による控除漏れ
ワンストップ特例の申請漏れや、確定申告書への記載漏れにより、本来受けられるはずの控除が適用されないケースがあります。必ず証明書類の管理と期限内の手続きを確認しましょう。
・法人は対象外
ふるさと納税は個人向けの制度です。法人が行う場合は「企業版ふるさと納税」として扱われます。個人と違い、地方自治体へ寄付を行っても返礼品を受け取ることは出来ません。
控除方法も異なりますので、詳しくは下記URLをご参照ください
地方創生2.0:企業版ふるさと納税ポータルサイト
https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/kigyou_furusato.html
まとめ
ふるさと納税は、制度を正しく理解し、適切に手続きを行えば非常にメリットの大きい制度です。一方で、税務上の注意点を見落とすと、意図せず損をしてしまう可能性もあります。
税理士法人ウィズでは、事業者向けにふるさと納税を含めた税金対策や節税支援、確定申告サポートも承っております!お気軽にご相談ください。